Edmundo Villani-Côrtesのページ
Edmundo Villani-Côrtesについて
エジムンド・ヴィラーニ=コルテス Edmundo Villani-Côrtes は1930年11月8日、リオデジャネイロの北130キロ位にあるミナス・ジェライス州ジュイス・ジ・フォーラ(ジュイス・デ・フォーラ)Juiz de Fora に生まれた。彼の父はフルート奏者で、また母はピアノが弾け、兄はギターが弾けたとのことで、父は自宅に仲間の音楽家を呼んではサラウ(個人宅に集まって音楽や踊り、詩の朗読など文化的活動をする集い)をしばしば催していたとのことである。ヴィラーニ=コルテスは子どもの頃から兄の持っていたギターやカヴァキーニョを弾いて遊んでいた。音楽家としては彼は晩期大成型で、17歳にして初めてピアノを習い始め、21歳でリオデジャネイロに出てブラジル音楽院でピアノを学んだ。
1954年にブラジル音楽院を卒業するとジュイス・ジ・フォーラへ戻り、翌1955年には地元のオーケストラとの共演で、自作の《ピアノ協奏曲第1番》を初演した。彼自身の言によると「このころ私は作曲のレッスンなど殆ど受けたことがなかった。ましてや管弦楽法など全く習ったことはなかった。グリーグのピアノ協奏曲がお手本だった」とのこと。
1959年に歌手のEfigênia Guimarães Côrtesと結婚し、一男二女をもうけている。1960年にはサンパウロに出てカマルゴ・グァルニェリに作曲を師事。ピアニストや編曲家として活動を始めている。1963年には歌手のピアノ伴奏の仕事でアルゼンチンとウルグアイに出かけている。
1968年にはブラジル映画『O Matador』の音楽を作曲。1970年よりテレビ局Tupiでピアニスト・編曲家として働き、千曲以上のポピュラー曲の編曲を手がけた。1973年にはサンパウロ音楽アカデミー Academia Paulista de Músicaで編曲と即興のレクチャーをしている。
1976年には、ブラジルで十二音技法を広めていた作曲家のハンス=ヨアヒム・ケルロイターに作曲を師事した(但しヴィラーニ=コルテスは「ケルロイターからは新しいことを学んだだけではなく、何をすべきでないかを学んだ」と意味深なことを述べている)。また1977年には《管楽四重奏と弦楽五重奏のための九重奏曲 Noneto》でブラジルゲーテ協会コンクール受賞をした。1982年からはサンパウロ州立大学で作曲法と対位法を教え、1999年の退職まで続けた。
1986年にはEditora Cultura Musical作曲コンクールで、ピアノまたはギターのための《気取ったショーロ Choro Pretensioso》(1983) が一等賞、ピアノ曲《リズム1番 Ritmata nº 1》(1985) が二等賞を得た。1990年には歌曲《セシリア・メイレレス連作 Ciclo Cecília Meireles》(1987) でサンパウロ芸術批評家協会 (A.P.C.A) より「1989年のベスト」賞を得た。A.P.C.Aからは1995年に合唱と管弦楽のための《サンパウロの絵葉書 Postais paulistanos》(1995)、1998年に《ビブラフォン協奏曲》(1994) も受賞作に選ばれた。2000年には《フルート協奏曲》がロンドンでコヴェントガーデン交響楽団により初演。同じく2000年にはジュイス・デ・フォーラ市制150年を記念して4重唱と管弦楽のための《テ・デウム Te Deum》(1999) が初演された。
90歳になった2020年現在も、お達者にされている。
ヴィラーニ=コルテスの作品は数百曲にのぼる。彼の作品は上記の経歴通り、ジャズ、ポピュラーからクラシック音楽、民族主義、印象主義、十二音技法まで色々な要素が混じっているのだけど、そのボーダレスな所がブラジルらしいです。ピアノ曲も同様に色々なジャンルの音楽に富んでいるが、全体的に親しみやすい旋律や和声の曲が多くお薦めです。
Edmundo Villani-Côrtesのピアノ曲リストとその解説
ヴィラーニ=コルテスの作品には原曲が歌曲やピアノ以外の楽器を含む合奏のために作られ、後に作曲家自身によってピアノ用にも編曲された曲がいくつもあります。それらのピアノ版編曲作品には * 印を付けました(原曲の作曲年ではなくピアノ用の編曲年でリストしました)。
1949-1956?
- Prelúdio nº 1, Moderato 前奏曲1番
ヴィラーニ=コルテスがピアノを習い始めたのは17歳であった1948年頃である。それまでの彼は、ギターやカヴァキーニョの演奏や、彼の優れた「耳」で音楽の響きについては十分に知っていたが、ショパンのピアノ曲を自ら練習することで「調性がどうなっているのか、ショパンは一つの和音から次の和音へとどのように移るのか」を興味津々で理解したとのことである。このショパンの音楽との出会いが彼の初めてのピアノ作品となる、9曲から成る「前奏曲」を作る大きな動機になったと思われる。一方和声の面からはドビュッシーの初期のピアノ曲の影響を強くている曲が多く見られる。第1番はハ長調。流れるような心地良い旋律が繰り返される。途中で変ホ長調に転調されたりするが、間もなく元のハ長調に戻り静かに終わる。 - Prelúdio nº 2, Moderato (1949) 前奏曲2番
変ホ長調。郷愁を感じさせるような五音音階の旋律が高音部で穏やかに奏される。 - Prelúdio nº 3, Lento 前奏曲3番
ニ短調。3連符混じりの、当てもなく彷徨うようなもの悲しい旋律が奏される。 - Prelúdio nº 4, Cantabile (con tranquilidade) 前奏曲4番
ヘ長調、A-A'-B-A"形式。ハープのような高音部アルペジオにのって、静かな旋律が奏される。長七の和音や属九の和音を多用した、ドビュッシー風の響きの曲。 - Prelúdio nº 5, Calmo bem ligado 前奏曲5番
ト長調、A-B-A'-コーダの形式。ワルツ風の曲。低音オクターブと両手和音が続くが、楽譜の指示通りpで穏やかに弾くのが相応しいであろう。 - Prelúdio nº 6, Allegretto (como o um regato, fluente) 前奏曲6番
ヘ長調、A-A-B-A形式。前奏曲の中でも、和音の美しさでは一番の曲。Aは静かな16分音符アルペジオのみから成り、七の和音や九の和音が遷ろうのが何とも魔法的な美しさだ。Bは旋律が現れ、ここも全音音階や転調などが絶妙な響きである。 - Prelúdio nº 7, Allegro 前奏曲7番
ト長調。左手アルペジオの伴奏にのって、右手におおらかな旋律が奏され、転調が頻繁。 - Prelúdio nº 8 前奏曲8番
ハ短調、A-A'-コーダの形式。重々しい気分の曲。A'の後半で半音づつ和音が下降する所はガーシュインの音楽を思わせる。コーダは突然低音・高音と炸裂するような強打音で終わる。
1950
- Estudo em nonas 陰気な練習曲
1951
- Estudo fantástico 幻想的な練習曲
1956
- Prelúdio nº 9, Moderato 前奏曲9番
変ホ長調。左手和音の伴奏にのって、郷愁溢れるような旋律がしっとりと奏される。
1957
- Série Brasileira opus 8 ブラジル連作集、作品8
ヴィラーニ=コルテスの作品では初期のもので、作曲技法はまだ荒削りといった感じだが、「ブラジル」を前面に出した興味深いピアノ曲集で、彼らしい独特の和音は不思議な感覚だ。- Prelúdio 前奏曲
ト短調、A-A'-コーダの形式。ギターのつま弾きを思わせる伴奏にのって、悲し気な旋律がゆっくりと奏される。 - Dança 踊り
A-B-A'-B'-A"-B"形式。Aはヘ長調で、長七の和音の平行移動と微睡むようなリズムはボサノヴァを思わせる。Bは目の覚めるような活発なシンコペーションのリズムからなる。この2つが形を変えながら繰り返され段々と盛り上がっていく。全体的に熱帯の夏の夜の夢をみているような幻想的な踊りのような曲。 - Movimento em três por quatro 4分の3拍子の楽章
変ニ長調、A-B-A'-B'形式。Aはひらひらと舞うような8分音符の旋律が艶やか。Bはしっとりとしたワルツが奏される。 - Chôro em forma de rondó ロンド形式のショーロ
A-B-A'-C-A-D形式。全曲軽快なリズムにのった曲で、Aの短三長六長九の和音はジャズっぽい。Cのオクターブで奏される低音レの連続はバイアォンのリズムで、それにのって奏される旋律はレのドリア旋法である。Cの中ほどには "IMP.AD LIB."(アドリブで弾くこと)と楽譜に指示された部分がある。奏者は勿論自分の作曲でこの部分を弾いてもいいが、ヴィラーニ=コルテス自身も35小節から成る楽譜を書いている。
- Prelúdio 前奏曲
1961
- Suíte infantil 子どもの組曲
- A pracinha das crianças 子どもたちの公園
- O concurso de papagaios 凧揚げ大会
- O dia de São Bartolomeu 聖バルトロマイの日
- Conversa com o vento 風を語る
1963
- Ponteio nº 1 ポンテイオ1番
- Ponteio nº 2 ポンテイオ2番
- Ponteio nº 3 ポンテイオ3番
- Ponteio nº 4 ポンテイオ4番
- Baião バイアォン
- Valsa ワルツ
1966
- Papagaio azul* 青い凧
原曲はヴィラーニ=コルテス自身の歌詞による、歌または児童合唱とピアノ(ト長調)の曲で、ピアノ用にも編曲された。曲の歌詞はブラジルの作家Regina Paleta Hargreavesの小説『太陽の日記 Diário do sol』を元にしている。小説はある貧しい少年が凧揚げ大会に出場する話で、歌詞は「行け、僕の青い凧、 行け、空へ昇れ、そして僕の心に新しい夢を持ってきて…」と歌っている。ピアノ版はへ長調、A-A'-B-A"。素朴ながら心温まる旋律で、旋律の下に添えられた密集和音の進行は半音階を多用して魅惑的な響きだ。Bは3拍子に変わり、いっとき変ロ長調になって空に舞い上がるような雰囲気になる。
1974
- Dia de descanso (para piano a quatro mãos) 休日(ピアノ連弾)
1976
- Timbre nº 1 打楽器1番
1976年にヴィラーニ=コルテスは一時的だが、ドイツ出身でブラジルに移住してきた作曲家ハンス=ヨアヒム・ケルロイター Hans Joachim Koellreutter (1915- 2005) に作曲を師事した。ケルロイターは無調主義と十二音技法をブラジルの作曲界に広めた人物であり、ヴィラーニ=コルテスが彼に「ピアノを旋律・和音楽器ではなく、打楽器として作曲してみなさい」と勧められて作った、無調の前衛的な作品である。第1番は演奏時間は1分少々。3音のクラスターとオクターブが時にはゆっくり時には速く、音量もffとppを対比させた曲。 - Timbre nº 2 打楽器2番
2分少々で、減二度の音が徐々に増していき、オクターブも加わって、クライマックスは両腕を使っての2オクターブ(右腕で黒鍵を、左腕で白鍵を叩く)のクラスター連打!。 - Timbre nº 3 打楽器3番
- Timbre nº 4 打楽器4番
1979
- Tema com variações 主題と変奏
- A catedral da Sé - Prelúdio em estilo Bachiano 大聖堂―バッハのスタイルによる前奏曲
ピアノ版以外にオルガン版と室内管弦楽版もある。ニ短調、A-B-A'形式。曲名通りのバッハ風の曲。Aは荘厳な和音が鳴り響く。Bは二声〜三声のポリフォニーとなる。 - Belibá (para piano a quatro mãos) ベリバ(ピアノ連弾)
ベリバとは、ヴィラーニ=コルテスが1975年に手に入れて飼っていた小鳥の名前で、その後この小鳥はフクロネズミに襲われて逃げてしまったと。ベリバの思い出を曲にしたこの作品は、郷愁たっぷりの美しい旋律の曲。変ホ長調、A-B-A'形式。 - Beiráceas (para piano a quatro mãos) ベイラセアス(ピアノ連弾)
ベイラセアスとは、ヴィラーニ=コルテスによる想像の花の名前とのこと。A-B形式。Aは静かに、Bは3-3-2のシンコペーションのリズムで、モダンジャズ風のクールな響きの曲。 - Valsinha de Roda* 回る小さなワルツ
原曲はヴィラーニ=コルテス自身の歌詞による、歌曲で、ピアノ用にも編曲された。ニ短調、前奏-A-B-A'形式。原曲の歌詞は、二人の過ぎ去った恋の始まりと終わりを回転するコマに例えて詠む内容で、曲はベースが半音階で下降する伴奏にのって、しんみりとした旋律が奏される。Bはへ長調になり昔を懐かしむような雰囲気で、Bの終わりは全音音階が魔法のように響いて、またAに戻る。
1980
- Balada para as flores 花々のためのバラード
変イ長調、 A-B-A'-コーダの形式。全曲しっとりとした美しい曲。Aは郷愁たっぷりの旋律が静かに奏される。Bはヘ長調の新たな旋律で少し情熱的に盛り上がる。A'は左手中声部に冒頭の旋律が現れ、コーダもこの旋律が何度も名残惜し気に奏される。ピアノ版以外にオルガン版もある。
1981
- Pretensioso, Chôro 気取って、ショーロ
この曲はピアノ版およびギター版の両方が作曲された。へ長調、A-B-A-コーダの形式。右手に16分音符の軽快な旋律が奏され、左手は主にブンンチャブンチャッの伴奏だが、時々バイシャリア(ショーロで低弦ギターが主旋律の合間に音階などの短い対旋律を合いの手のように入れること)を思わせる16分音符パッセージが現れる。Bはへ短調で始まり、転調が頻繁。
1983
- Prelúdio e fuga 前奏曲とフーガ
1985
- Ritmata nº 1 リズム1番
ニ短調、前奏-A-A'-A"-A"'-コーダの形式。レシタティーヴォ風の前奏に引き続き、Aは左手にシンコペーションの効いたオスティナートの伴奏が続き、それにのってラが♭になっている(ブルー・ノート・スケールに近い)憂うつな雰囲気の旋律がpで奏される。A'は旋律が完全四度の重音になり、対旋律も加わってfで奏される。A"は右手旋律、左手オスティナートの伴奏ともにオクターブとなり、fffでうるさく奏される。A"'は再び静かになり、コーダは高音部に神秘的なアルペジオが鳴って終わる。 - Ritmata nº 2 リズム2番
1986
- Ponteio nº 5 ポンテイオ5番
1990
- Caetê Jururê (para dois pianos)* カエテ・ジュルレ(2台ピアノ)
- Canção de Carolina* カロリーナの歌
ヴィラーニ=コルテスの孫娘カロリーナが生まれたのを記念して作った曲で、原曲はJúlio Bellodiの作詞による歌曲だが、このピアノ版の編曲がある。変ロ長調、前奏-A-A-A'-後奏の形式。落ち着いたワルツで、優しい眼差しのような旋律と、マイナーコードやテンションコードを織り込んだ和音進行がお洒落。
1991
- Alma de natureza* 自然の命
原曲はフルートとピアノのための組曲《ブラジル連作集 Série Brasileira》の第1曲〈ポンテイオ Ponteio〉(へ長調)で、《自然の命》と曲名を変えた歌曲版やこのピアノ版の編曲がある(因みにヴィラーニ=コルテスは1957年に同じ題名のピアノ独奏曲集《ブラジル連作集、作品8》を作曲していて混同しやすいが、全く別の曲である)。変イ長調、A-B-A'-コーダの形式。左手8分音符が川の流れのようにさらさらと奏されるのにのって穏やかな旋律が奏される。 - Chôro* ショーロ
原曲はフルートとピアノのための組曲《ブラジル連作集 Série Brasileira》の第4曲〈ショーロ Chôro〉で、このピアノ版の編曲がある。ハ長調、A-B-A-C-A-コーダの形式。ブチャンチャブチャンチャの左手伴奏にのって、跳ねるような16分音符の旋律が奏される。Bはイ短調に、Cはへ長調になる。このフルートとピアノのための《ブラジル連作集》は、第1曲〈ポンテイオ〉の穏やかな雰囲気、第4曲〈ショーロ〉の跳ねるような軽快な雰囲気いずれも、正にフルートの響きにピッタリの作品で見事である。 - Casulo* 繭
原曲はJúlio Bellodiの作詞による歌曲だが、このピアノ版の編曲がある。A-B-C形式。晩秋を思わせるような哀愁たっぷりの曲で、Aはト短調で、Bは頻繁に転調し、Cはハ短調になる。
1993
- Balada dos 15 minutos* 15分間のバラード
原曲はテナーサックスとピアノのために書かれた曲で、ヴィラーニ=コルテスの息子で作曲家・クラリネット・サックス奏者のエド・コルテス (1965-) が留学するに当たってのはなむけとして15分で作曲したとのこと。Júlio Bellodiの作詞による歌曲版およびピアノ版の編曲がある。ハ長調、A-A'-B-A"形式。ゆったりとしたバラードで、テンションコード満載のジャズ風の和音進行とお洒落な旋律ははテナーサックス向けの曲に相応しい雰囲気。Bは変ホ長調〜変ト長調と転調する。 - Rua Aurora* アウロラ通り
原曲はマリオ・ジ・アンドラージ (1893-1945) の詩による歌曲である。詩人・民俗学者・音楽評論家であったマリオ・ジ・アンドラージの生誕百年を記念してサンパウロ市が催した作曲コンクールで、この曲は賞を得た。ピアノ版の編曲がある。ニ長調。バラード風の曲で、語りかけるような旋律が奏される。
1994
- Pedrinho's boogie ペドリーニョのブギ
- A primeira folha do diário de um saci あるサシーの日記の1ページ目
- Sonata ソナタ
ヴィラーニ=コルテスの二人の孫に献呈された作品。- Lenda 昔話
この曲について「昔話を子どもに語る光景を描いた」と作曲者自身が語っている。ソナタ形式。ハ長調の第1主題、ト長調の第2主題ともに優しく穏やかな曲調で、響きはドビュッシーの初期を思わせる。展開部は両主題がアルペジオの伴奏にのって夢のように奏され、再現部は両主題ともハ長調で静かに終る。 - Cantilena カンチレーナ
A-A'形式。一応イ短調だが、半音階的な和音進行が神秘的で、寂し気な雰囲気。サティのジムノペディに似ている。 - Corrupio コフーピウ
コフーピウとは手を組んでぐるぐる回る子どもの遊びのこと。殆ど単音で、時たま二声になるのみの落ち着きない乾いた響きの旋律が上へ下へと奏される。自筆譜では調号はついていないが、変ホ長調から始まりどんどん転調していく。以上、第1楽章はロマンティック、第2楽章は神秘的、第3楽章はちょっと新古典主義な響きと、変わったソナタだな~。
- Lenda 昔話
1995
- Ritmata nº 3 (revisão 2008) リズム3番(2008年に改訂)
- Chôro do João* ジョアンのショーロ
- Luz* 光
原曲はクラリネットとピアノのために書かれた曲で、ピアノ用にも編曲された。変イ長調、A-B-A'形式。アルペジオの伴奏にのって、ゆったりとした旋律が奏される。Bはいっときニ長調になる。
1996
- Sonatina ソナチネ
全曲通して僅か2分半位の短いソナチネで、ヴィラーニ=コルテス自身は「ピアノを習って数年の子供のために、たった約30分で作曲した」と述べている。- Ingênuo 無邪気に
ト長調。16分音符の二声の旋律が遊び回るように奏され、すっと消えるように終わる。 - Tristonho 悲しげに
ト短調。これも二声の旋律がしみじみ悲しげに奏される。 - Agitado 興奮して
ト長調。両手交互連打が騒がしい曲。
- Ingênuo 無邪気に
- Poema brasileiro ブラジルの詩
1997
- Música de Pularia
- O Gabriel chegou* ガブリエウが来た
ガブリエウはヴィラーニ=コルテスの孫の名前。原曲はテナーサックスとピアノのために書かれた曲で、ピアノ用にも編曲された。ト長調、前奏-A-B-B-A-C-C'-A-コーダの形式。可愛らしい孫への祖父の優しい眼差しが伝わってくるような曲。Aは16分音符の旋律が上下して、やんちゃな孫を描いているよう。Bはニ長調になり、ナザレのピアノ曲《アトゥレヴィード》や《オデオン》に現れるようなオクターブ和音の16分音符3連打が続く。Cはハ長調になり、のびやかな旋律の下で、シンコペーションの和音が連打で鳴る。
1998
- Clara クララ
- O orelha* 耳
原曲は1983年にクラリネットとピアノのために書かれた曲で、1998年にピアノ用に編曲された。変ロ長調、前奏-A-A-B-B'-A-C-D-A-A'形式。ズチャンチャの左手伴奏にのって愛嬌ある旋律が奏される。Bはト短調、CとDは変ホ長調になる。 - Poranduba (para piano a quatro mãos)* ポランドゥーバ(ピアノ連弾)
- Prelúdio Op. 2, nº 9, Rítmico com simplicidade 前奏曲、作品2、9番
《前奏曲9番》と題され1956年に作曲された曲は既に存在していて、前奏曲集の中でこの一曲のみがブラジルの楽譜出版社Irmãos Vitaleより出版されている。ブラジルの出版社Estúdio Dois Produções Culturaisが1998年頃に楽譜集『ピアノのための10つの前奏曲集と5つの間奏曲集 Dez prelúdios e cinco interlúdios para piano』の出版を計画し、著作権を持つIrmãos Vitale社に同曲の再出版の許諾を得ようとしたところ、高額の支払いを求められた。新たな楽譜集の出版はヴィラーニ=コルテス自身も望んでいたことであり、そこで彼は新たに作曲したのがこの《前奏曲、作品2、9番》で、同楽譜集は2000年に出版された。楽譜に調号は記されていないが、ハ短調に近いが、ソが♭のほぼブルース・スケールの小品。 - Prelúdio nº 10, Moderato 前奏曲10番
ヴィラーニ=コルテスが1978年に作曲した《5つのブラジルの細密画 Cinco miniaturas brasileiras》は元はリコーダーとピアノのための組曲だが、ピアノトリオや弦楽オーケストラなどにも編曲され、彼の代表作として知られている(2006年の項も参照)。この組曲の第1曲〈前奏曲 Prelúdio〉を、ヴィラーニ=コルテス自身が1998年にピアノ独奏用に編曲したもの。メロディーメーカーであるヴィラーニ=コルテスのピアノ曲の中でも、屈指の悩ましい調べ?の曲。イ短調、前奏-A-B-A'-コーダの形式。雨がしとしと降るような寂しげな左手伴奏にのって、哀愁たっぷりの旋律が奏される。
1981-1999
- Álbum de chôros ショーロのアルバム
ヴィラーニ=コルテスが今迄に作曲した曲(他楽器をピアノ版に編曲したもの)および書き下ろしのピアノ曲を10曲のアルバムとして纏めた楽譜集だが未出版で、私も3曲の自筆譜のコピーを持っているのみです。- Os chorões da Paulicéia (1998) サンパウロのショーロ
- O orelha* (1998) 耳
- Chôro do João* (1995) ジョアンのショーロ
- O Gabriel chegou* (1997) ガブリエウが来た
- Chôro urbano* (1990) 都会のショーロ
- Chôro miniatura ミニチュアのショーロ
- Chôro das madrugas 早朝のショーロ
- Chôro patético (1999) 悲痛のショーロ
- Canhoto também tem vez (1999)
- Pretensioso, Chôro (1981) 気取って、ショーロ
1999
- Interlúdio, nº 1, Molto expressivo 間奏曲1番
楽譜の冒頭には「7世紀に亘るムーア人の支配は、イベリア半島の音楽に強い影響を与えた・・・」と記されている。イ短調、A-A'-A形式。サラバンド風で、いにしえに思いを馳せるような響きの曲。 - Interlúdio, nº 2, Moderato expressivo - Vivace 間奏曲2番
「ピアノの名人達は、貴族の館での夜のパーティーでその腕前を披露する・・・」と記されている。変ロ長調。ゆったりとした前奏に引き続き、豪華なパーティーを彷彿させるような旋律が急き立てられるように奏される。 - Interlúdio, nº 3 間奏曲3番
ハ長調、A-B-B-A'形式。ナザレやシキーニャ・ゴンザーガの時代を思わせるショーロが陽気に奏される。 - Interlúdio, nº 4, Lento (saudoso) 間奏曲4番
「たくさんの音、たくさんのファンタジー、たくさんの心、たくさんの喜び、たくさんの郷愁、たくさんのサウダージ、たくさんの優しさ、たくさんの希望、全てたくさん・・・」と記されている。ヘ長調、A-B-A'形式。お洒落な和音の伴奏にのって、穏やかな旋律が奏される。中間部は変イ長調になる。 - Interlúdio, nº 5, (com uma certa liberdade) 間奏曲5番
「我々の吸う空気、着る服、会う人々、疑い、信仰、全ては音楽を導き、それは毎日、毎時異なる表情を見せる・・・」と記されている。変ホ長調、A-B-A形式。これもお洒落な和音にのって、夜の情景を思わせるような旋律がしっとりと奏される。
2001
- Adágio アダージオ
2002
- Melodia para Luciana ルシアーナのためのメロディー
2003
- Festiva, Valsa 陽気な、ワルツ
変ホ長調、前奏-A-B-A-コーダの形式。1小節=88と楽譜に指定された速いテンポの曲。陽気に跳ね回るような雰囲気の旋律が続く。Bは変イ長調で始まり、速いテンポながらも3連符混じりの甘えるような旋律になる。 - Saudosa, Valsa 懐かしい、ワルツ
ホ短調、A-B-C-B-A-B形式。所謂ヴァルサ・ブラジレイラ(ブラジル風ワルツ)の雰囲気の曲。哀愁を秘めたような旋律が奏される。Aの途中で4小節だけロ長調に転調する所は突飛な響き。Bはテンポを速めて8分音符の旋律が吹き抜けるように流れる。Cはト長調になり、落ち着いた感じになる。
2005
- Águas claras* 澄んだ水
- V Estação da Via Sacra "Simão Cirineu ajuda a Jesus" - A segunda queda de Jesus 十字架の道行きの第5留「キレネのシモンは十字架を担ぐのを助ける」 - イエスは再び倒れる
「十字架の道行き」とはカトリック教会の信心業で、イエス・キリストの死刑の宣告から十字架上で亡くなり埋葬されるまでが14の留(復活の場面を含めると15留)に分かれていて、カトリック教会では14枚の絵または彫刻が架けられている。ブラジルの作曲家Sergio Chneeが「十字架の道行き」の各留を印象としたピアノ曲の作曲を12人のブラジルの作曲家に委嘱し(Sergio Chnee自身も3曲作り)、集められた15曲は2013年にCD「Via Sacra」としてリリースされた。ヴィラーニ=コルテスが作曲したのは〈第5留「キレネのシモンは十字架を担ぐのを助ける」〉である。曲は前奏-A-A'-A"-A-A'-コーダの形式。葬送行進曲を思わせるようなゆっくりとした低音オスティナートにのって、意味深長な旋律が繰り返される。
2006
- Cinco miniaturas brasileiras* 5つのブラジルの細密画
《5つのブラジルの細密画》は元はリコーダーとピアノのための組曲だが、ピアノトリオや弦楽オーケストラなどにも編曲され、彼の代表作として知られている。ヴィラーニ=コルテスは1998年に《前奏曲10番》の曲名で第1曲をピアノ独奏版に編曲し、また後に残り4曲も全てピアノ独奏版に編曲している。- Prelúdio 前奏曲
1998年の《前奏曲10番》と同一の編曲。 - Toada トアーダ
ト長調、A-B-A'形式。左手♩. ♩. ♩のシンコペーションのリズムにのって、素朴な旋律がソのミクソリディア旋法で奏される。 - Choro ショーロ
ハ長調、A-B-A'形式。Aは跳ねるような右手旋律の下で、左手が16分音符で対旋律を奏でる。 - Cantiga de ninar 子守歌
へ長調、A-B-A'形式。郷愁を感じさせうるような旋律が穏やかに奏される。 - Baião バイアォン
一応ニ長調。バイアォンのリズムにのってレのミクソリディア旋法の旋律が陽気に奏される。
- Prelúdio 前奏曲
- Coração latino (para dois pianos) ラテンの心(2台ピアノ)
- A pororóca ポロロッカ
ポロロッカとは、アマゾン川周辺のいくつかの川(アラグァリ川やグアマ川)で見られる海嘯(河口に入る潮波が川を逆流する現象)のこと。ポロロッカは5メートルもの高さの波が逆流して川を上り、数百キロ内陸まで達することもある。A-B-A'形式、強いて言えばト長調。無窮動で続く16分音符が騒がしい曲で、最初は高音部で始まるも、中音部の両手交互連打、低音部からうねるように押し寄せる波のような上行半音階と展開し面白い。
2007
- Rue Ramponeau ランポノー通り
フランスの画家ジャン=ジャック・オスティエ Jean-Jacques Ostier (1945-2011) が2000年に描いたリトグラフ『Rue Ramponeau』に印象を受けて作曲され、オスティエに献呈された(オスティエの『Rue Ramponeau』などの作品はここで見れます)。ヘ長調、前奏-A-A'-B-A-A"-コーダの形式。対旋律の半音階進行やテンションコードなどのお洒落な和音が何ともいい雰囲気の、落ち着いたワルツ。Bは変イ長調〜ロ長調になる。 - Reflexos 反射
2011
- Ânfora アンフォラ
2014
- Choro dengoso 気取ったショーロ
楽譜には「比類のない故エルネスト・ナザレに謹んで敬意を表して」と記されている。ニ短調、A-B-A-C-A-コーダの形式。付点やシンコペーションのリズムで奏される音楽はナザレ風であるが、半音階進行とか、属七の和音に9度や13度を加えたりとかなどはヴィラーニ=コルテスらしいお洒落な雰囲気。Bはヘ長調になり、高音部の16分音符の旋律が煌びやかな響き。Cはニ長調になり、両手オクターブが華やか。 - Lili リリ
リリとは、ヴィラーニ=コルテスの義娘でバレエダンサー・振付家であるLiliane de Grammontの愛称である。Liliane de Grammontがバレエのレッスンを授けるのに適した簡単な音楽が無いと言ったのをヴィラーニ=コルテスが聞き、この曲を作ったとのこと。へ長調、A-A'-B-C-A'形式。左手3拍子の伴奏にのって、あどけない旋律が奏される。Bはいっとき変イ長調になりロマンティックな雰囲気だ。Cはスタッカートの連続で愛嬌たっぷり。 - Valsa brilhante, em homenagem ao compositor Marcello Tupynambá 華やかなワルツ、作曲家マルセロ・トゥピナンバに敬意を表して
マルセロ・トゥピナンバ Marcello Tupynambá(Marcelo Tupinambáと綴ることも多い、1889-1953)は歌曲やピアノ曲を多数作ったブラジルの作曲家。変ホ長調、A-B-A-C-A-コーダの形式。速いテンポの軽快なワルツの伴奏にのって、右手に8分音符が続く旋律が煌びやかに奏される。Bは変イ長調になり、少しテンポを落として優雅なワルツとなる。Cも変イ長調になるが、ここでは旋律は高音部8分音符に加えて、華やかなオクターブも現れる。
2017
- Gugú, Choro esperto! ググ、活発なショーロ!
ヴィラーニ=コルテスのひ孫であるGustavoに献呈された。GugúはおそらくGustavoの愛称であろう。ト長調、前奏-A-A-B-A-コーダの形式。いたずらっぽい前奏に引き続き、速いテンポのシンコペーションの伴奏にのって、16分音符が続く快活な旋律が奏される。Bはホ短調になり、両手共ほとんど16分音符の連続で愛嬌たっぷり。ナザレのピアノ曲を少し思わせる。
Edmundo Villani-Côrtesのピアノ曲楽譜
Irmãos Vitale
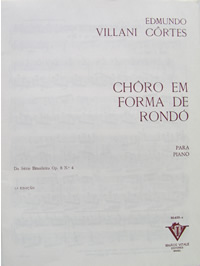 |
|
Cultura Musical LTDA.
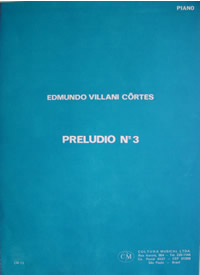 |
|
Ricordi Brasileira S.A.
- Ponteio Nº 2
Estúdio Dois Produções Culturais
- Dez prelúdios e cinco interlúdios para piano
斜字は絶版と思われる楽譜
Edmundo Villani-Côrtesのピアノ曲CD
星の数は、![]()
![]()
![]() は是非お薦めのCD、
は是非お薦めのCD、![]()
![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、
は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCDです。
はどうしてもという人にお薦めのCDです。
Luciana Hamond interpreta Villani-Côrtes - Prelúdios, Interlúdios e Canções para piano solo![]()
![]()
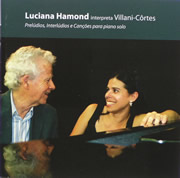 |
|
Luciana Hamond (pf)
2007、2008年の録音。
Grupo AUM Interpreta Villani-Côrtes![]()
![]()
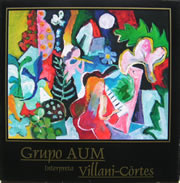 |
|
Grupo AUM: Arlete Tironi Gordilho (pf), José Roberto Capel Cardoso (pf), Liliana Bertolini (flauta), André Geiger (contrabaixo), Piero Damiani (pandeiro convidado)
2001年の録音。
Te Deum![]()
Centro Cultural Pró Musica de Juiz de Fora
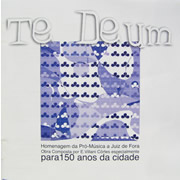 |
|
Edmundo Villani Cortes - OPUS 80![]()
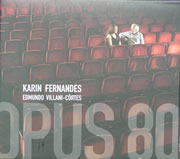 |
|
Karin Fernandes (pf)
Música, Doce Música, RECITAL![]()
Paulinas COMEP, CD 11727-7
 |
|
Eudóxia de Barros (pf)
1997、1998、1999、2001年の録音。
Compositores Latino-Americanos 7![]()
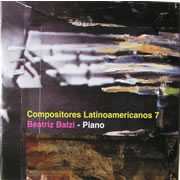 |
|
Beatriz Balzi (pf)
2000年の録音。
Sonata Brasileira![]()
Odradek Records, ODRCD332
- Sonata in A (André Mehmari)
- Sonata (Camargo Guarnieri)
- Sonatina, Hommage à Francis Poulenc (Marcelo Amazonas)
- Sonata n.1 in C (Edmundo Villani Côrtes)
Antonio Vaz Lemes (pf)
2012年の録音。
Páginas do Piano Brasileiro - Compositores e Intérpretes Brasileiros![]()
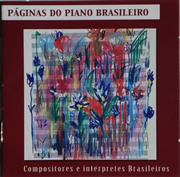 |
|
Via Sacra - Piano Brasileiro Contemporâneo IV![]()
- 1ª Estação, Jesus é condenado à morte (Sergio Chnee) (Paulo Gazzaneo, pf)
- 2ª Estação, Jesus carrega a pesada cruz (Diogo Lefèvre) (Rogério Zaghi, pf)
- 3ª Estação, Jesus cai pela primeira vez (Rodolfo Coelho de Souza) (Rogério Zaghi, pf)
- 4ª Estação, Jesus encontra a sua Mãe Santíssima - meditação para piano (Almeida Prado) (Paulo Gazzaneo, pf)
- 5ª Estação, Simão Cirineu ajuda a Jesus - A segunda queda de Jesus (Edmundo Villani-Côrtes) (Paulo Gazzaneo, pf)
- 6ª Estação, Verônica limpa o rosto de Cristo (Amaral Vieira) (Rogério Zaghi, pf)
- 7ª Estação, Jesus cai pela segunda vez - La seconde chute (Jorge Antunes) (Rogério Zaghi, pf)
- 8ª Estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém - Antifonias (Eduardo Guimarães Álvares) (Rogério Zaghi, pf)
- 9ª Estação, Jesus cai pela terceira vez (Sergio Chnee) (André Pédico, pf)
- 10ª Estação, Jesus é despojado de suas vestes - Sem título, Só-nus (Silvia de Lucca) (Paulo Gazzaneo, pf)
- 11ª Estação, Jesus é pregado na cruz - Crucifixus (Mario Ficarelli) (Rogério Zaghi, pf)
- 12ª Estação, Jesus morre na cruz (Achille Picchi) (Rogério Zaghi, pf)
- 13ª Estação, Jesus é entregue à sua santa Mãe (Ricardo Tacuchian) (Paulo Gazzaneo, pf)
- 14ª Estação, Jesus é sepultado (Kilza Setti) (Rogério Zaghi, pf)
- 15ª Estação, Ressurreição (Sergio Chnee) (Paulo Gazzaneo, pf)
Edmundo Villani-Côrtesに関する参考文献
- Música contemporânea brasileira: Edmundo Villani-Côrtes. Centro Cultural São Paulo 2006.
- Ednaldo Camelo Borba Junior. Nationalism in Two Works by Edmundo Villani-Côrtes. University of Oregon 2018.
- Luciana Hamond. Onze prelúdios para piano solo de Edmundo Villani-Côrtes: uma análise para a compreensão do potencial didático da obra para o desenvolvimento de habilidades técnico-interpretativas. Revista Orfeu do Programa de Pós-Graduação em Música, v. 5 n. 2. Centro de Artes, Moda e Design (CEART) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 2020.